| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※初診の方の受付は19時まで
\ お電話はこちらから /
0422-38-8708
\ 24時間予約受付中 /
\ 当日予約OK! /
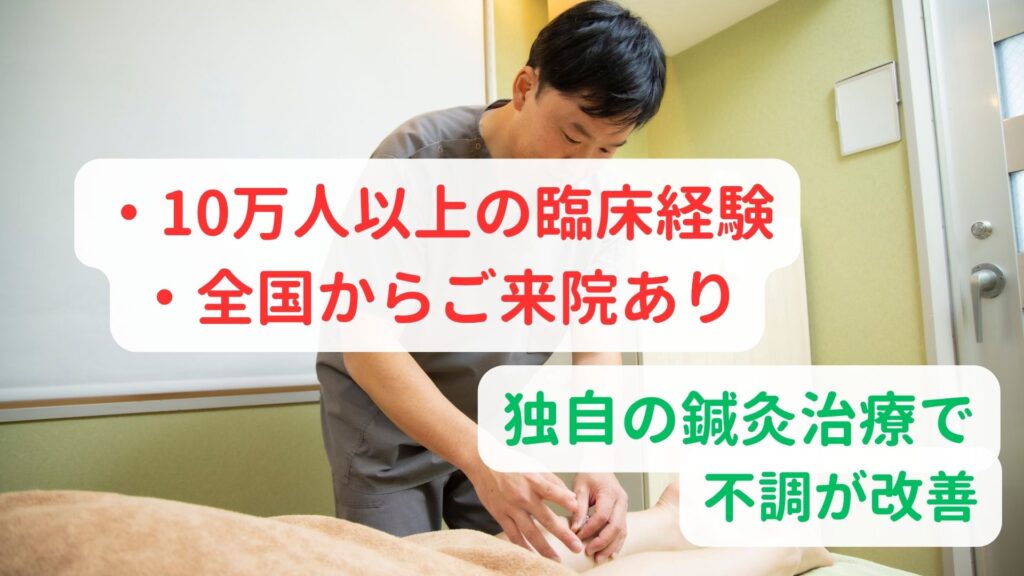
このブログを監修している鈴木貴之は国家資格であるはり師免許、きゅう師免許、柔道整復師免許、心理カウンセラーを取得した資格保有者です。
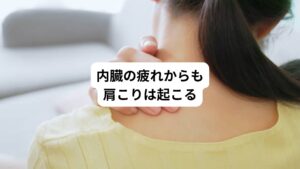
「お酒を飲み過ぎた翌日に肩こりを強く感じる」
「お腹の調子が悪い時に首もこった感じがする」
このような肩こりを経験したことはないでしょうか。
その他にも以下の生活習慣で肩こりや首こりがつらい方はおられないでしょうか。
・毎晩お酒を飲んでいる方
・間食が多い方
・いつも早食いの肩
・大食いの方
このような方の場合、内臓の疲労からくる肩こりが起きている可能性があります。
肩こりというとデスクワークやスマホなどの作業姿勢が大半の原因です。
しかし、実は内臓が疲れてしまっていても肩こりや首こりは起こります。
そこで今回は「飲酒と肩こりの関係について|飲みすぎで内臓が疲労すると肩こりが起こる」と題して内臓の疲れと肩こりの意外な関係性について解説します。
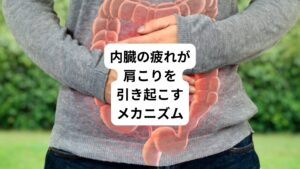
身体には神経反射という働きがあります。
たとえば膝を叩くと足が伸びる脚気の検査に使われるのも神経反射です。
また転びそうになったときに手が出るのも神経反射です。
その神経反射の中には内臓と皮膚をつなぐ神経回路があります。
そのため内臓に負荷がかかると特定の皮膚や筋肉が硬くなるという神経反射が起こります。
その神経反射の中には首や肩との関係が以下のようにあります。
・肝臓(かんぞう)に負担が掛かると右の首が痛くなる
・膵臓(すいぞう)に負担が掛かると左の首が痛くなる
肝臓が疲れやすい原因には主にお酒の飲みすぎ、薬の飲みすぎ、目の使い過ぎ、イライラしすぎなどがあります。
また膵臓(すいぞう)はインスリンを出す働きがあります。
そのため糖分の取り過ぎ、大食い、早食いが主な原因となります。
特に負担となりやすいのが飲み会です。
忘年会や歓送迎会などのシーズンは飲み会も多く、肝臓と膵臓は負担が掛かりやすくなります。
そのためお酒を飲んだ翌日に首を寝違えることは多くあります。
飲みすぎて内臓に負担が掛かり、その刺激が神経反射となって肩こりや首こりを強めてしまい、結果的に痛めてしまいます。
簡単に自分で出来る肝臓の疲れを解消させるセルフケアをお伝えいたします。

【ツボの場所と刺激方法】
足の親指と人差し指の付け根の交わるところにあります。
小さく円を描くように痛気持ちいいくらいの強さで揉んでください(15秒~30秒)
肝臓は腹部の右側にあるのでとくに右足の太衝を刺激するようにしましょう。
またせんねん灸などのお灸をお持ちの方はここにお灸をすると効果は更に高まります。
熱を感じるまで置いてみましょう。

右の肋骨周りは肝臓の影響を受けています。
肝臓に負担が掛かり血流が悪くなると右の肋骨周りも硬くなるため、ここをほぐしてあげましょう。
【マッサージ方法】
①両手を重ねて手のひらを右の肋骨の上に当てます。
②その状態で少し圧迫しながら円を描くようにマッサージします。
③15秒~30秒続けてマッサージする。
※あまり強く押すと肋骨を痛めてしまう可能性があるため、適度な強さで押しましょう。
もし、行っている最中に気分が悪くなったりする場合は中止してください。
日々のケアとしてすることをお勧め致します。
膵臓の疲労を解消させるセルフケアも解説します。
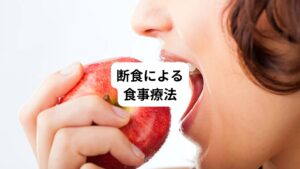
膵臓の疲れを解消させるために一番良い方法はプチ断食です。
まずは夕食から抜いてそのまま早めに寝るようにしましょう。
膵臓に負担をかけるのは主に糖分です。
夕食を抜くことで膵臓に負担が掛かることがなくなり、睡眠によってしっかり疲労が回復するようになります。
「お腹空いたままでも大丈夫なのか」と思われるかもしれません。
しかし現代人は基本的に食べすぎなので一日の一食くらい抜いても何も問題はありません。
疲れすぎて食欲が湧かないときは一日何も食べない日があってもかまいません。
ただし水分や塩分は少量取るようにしてください。
何も摂取しないと熱中症や脱水症の危険性があります。
またどうしてもお腹が空いて耐えられないというときは白ご飯ではなく卵やナッツなどの油分やビタミン、ミネラルが多い食材を食べるようにして、糖分は取らないようにしましょう。
これを2,3日続けるだけでもかなり膵臓の負担は減り回復します。

慢性的な肩こりでお悩みの方は当院で行っている神経解放テクニックで改善できます。
神経解放テクニックは整体と鍼灸を組み合わせた当院独自の治療法です。
この治療法によりあなたのつらい肩こりも完治させることができます。
長年悩まれている肩こりでお悩みの方はぜひ当院にご相談ください。
